編集後記を書くとき、「何を書けばいいのか分からない」「毎回同じ表現になってしまう」と悩んだことはありませんか?
特に秋は、季節感を出しやすい一方で、同じような表現になりがちです。
この記事では、そんなお悩みを解消するために、秋(9月〜11月)にぴったりな編集後記の構成ルールや、すぐに使える例文、便利なフレーズをまとめてご紹介。
企業広報誌・社内報・学校・地域向け・カジュアル用途まで網羅し、短文・中文・フルバージョン例文を豊富に掲載しています。
「読者の心に響く編集後記」をスムーズに仕上げたい方は、ぜひ参考にしてください。
秋の編集後記とは?役割と魅力
秋の編集後記は、記事や冊子の最後にそっと添える「あとがき」のような存在です。
単なる締めの言葉ではなく、読者との心の距離を縮める役割を担っています。
この章では、編集後記の基本的な意味と、秋という季節だからこそ書く価値について解説します。
編集後記の基本的な役割
編集後記とは、記事や冊子の末尾に設けられる短いコラムです。
編集者や制作者の目線で、記事全体を振り返ったり、制作の裏話を共有したりする場所として活用されます。
肩の力を抜いた語り口が歓迎されるパートで、フォーマルな本文とは違い、読者との関係性を温める効果があります。
たとえば、「今号を担当して、個人的に感じたこと」や「最近ちょっと気になっていること」など、ほんの少しだけパーソナルな話題を加えると、読者はその声に親しみを感じてくれます。
秋に書くことで伝えられる季節感
では、なぜ「秋の編集後記」が特におすすめなのでしょうか?
それは秋という季節が、自然・文化・暮らしの変化を感じやすいタイミングだからです。
木々の紅葉、月見、お祭り、ハロウィンといった風物詩に加え、「○○の秋」という言い回しがあるように、スポーツや芸術、読書など、話題のネタも豊富です。
こうした秋らしい出来事や雰囲気を編集後記に織り交ぜると、記事に季節感を与え、読者に共感や癒やしを届けることができます。
特に紙媒体やWebマガジンなどで、硬めの情報が続いたあとには、ちょっと柔らかい「人の声」が感じられるコーナーが必要です。
秋の編集後記は、そうした「余白」や「余韻」を読者に提供できる貴重なパートなのです。
| 役割 | 秋の編集後記が得意とすること |
|---|---|
| 季節感の演出 | 紅葉・月見・ハロウィンなど秋の話題を盛り込みやすい |
| 親しみやすさ | パーソナルな語り口で読者に近づける |
| 読後の満足感 | 硬い内容のあとに“余韻”を残すコーナーとして機能 |
つまり、秋の編集後記は、情報と感情をバランスよくつなぐ「最後のひと押し」なのです。
秋の編集後記を書く基本ポイント
秋の編集後記は、ただ「秋らしい言葉を入れれば良い」というわけではありません。
読者の心に届く編集後記を書くためには、いくつかの基本ポイントを押さえることが大切です。
この章では、構成の流れと表現の工夫について、具体的に解説していきます。
時候の挨拶で自然に始める
まず冒頭では、季節に合った時候の挨拶を使って秋の空気感を一瞬で伝えましょう。
たとえば「秋晴の候」や「爽秋の候」など、9〜11月の時期に応じた挨拶がよく使われます。
丁寧な印象を与えるだけでなく、文全体のトーンを整える効果もあります。
秋の自然や行事を盛り込む
読者との共通点を作るうえで、紅葉や月見、文化祭、ハロウィンなど、身近な季節ネタはとても効果的です。
地域の秋祭りの話、街で見かけた風景など、小さな出来事でも共感を呼びやすくなります。
体験談や気づきを添える
個人的な体験や気づきを一言加えることで、文章にあたたかみや「人間らしさ」が生まれます。
たとえば「先日、近所の公園でどんぐりを拾って…」といった些細な話題でも、読者は「自分ごと」として受け止めやすくなります。
読者への気遣いと前向きな締め
終わりの一文では、読者に向けたちょっとした気づかいを添えると、印象がグッと良くなります。
ただし、YMYLに抵触しないよう、健康や病気に触れるのではなく、「秋が深まる中、どうぞご自愛ください」のように抽象的な表現を選びましょう。
また、締めの言葉には、「実り多き秋となりますように」などの前向きなメッセージが効果的です。
| ポイント | 具体的な工夫例 |
|---|---|
| 冒頭 | 「爽秋の候」「秋晴れの空のもと」などの時候の挨拶 |
| 季節ネタ | 紅葉狩り、月見団子、ハロウィン、文化祭 |
| 体験談 | 「近所の公園で秋の花を見つけました」など |
| 締め | 「皆さまにとって心豊かな秋となりますように」 |
以上の5ステップを意識することで、秋らしく共感される編集後記が自然に書けるようになります。
秋の編集後記に使える時候の挨拶例(9月〜11月)
編集後記の冒頭に入れる「時候の挨拶」は、文章全体に季節感と丁寧さをもたらします。
ここでは、9月・10月・11月それぞれの月にふさわしい表現と、実際に編集後記で使える例文を紹介します。
読者の体感と季節のずれがないよう、時期に合った挨拶を選ぶのがポイントです。
9月に使える表現と例文
| 表現 | 使える時期 |
|---|---|
| 残暑の候 | 9月上旬 |
| 秋晴の候 | 9月上旬~中旬 |
| 爽秋の候 | 9月中旬~下旬 |
| 初秋の候 | 9月全般 |
| 秋涼の候 | 9月中旬以降 |
例文:
・秋晴れの日が続き、朝夕の空気に秋の訪れを感じる頃となりました。
・爽秋の候、皆さまはいかがお過ごしでしょうか。
・初秋の気配が漂う今日この頃、街の風景にも変化が見えはじめました。
10月に使える表現と例文
| 表現 | 使える時期 |
|---|---|
| 秋涼の候 | 10月初旬~中旬 |
| 紅葉の候 | 10月中旬~下旬 |
| 錦秋の候 | 10月中旬以降 |
| 清秋の候 | 10月全般 |
| 秋冷の候 | 10月中旬~下旬 |
例文:
・紅葉の候、日中の空気にも冷たさが感じられるようになってきました。
・秋冷の候、風に色づく木々が季節の深まりを知らせてくれます。
・錦秋の趣が増すこの頃、皆さまにとって穏やかな日々でありますように。
11月に使える表現と例文
| 表現 | 使える時期 |
|---|---|
| 晩秋の候 | 11月全般 |
| 深秋の候 | 11月中旬~下旬 |
| 初冬の候 | 11月下旬~ |
| 小春日和の候 | 11月全般(穏やかな日) |
| 向寒の候 | 11月下旬~ |
例文:
・晩秋の候、木々の色づきもいよいよ鮮やかになってまいりました。
・深まる秋の空気が心地よく、小春日和に恵まれる日も増えてきました。
・初冬の足音が近づくなか、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
※地域によって季節感に差があるため、実際の気候に合った表現を選ぶようにしましょう。
これらの挨拶を組み合わせることで、毎回違った表情のある編集後記が書けます。
秋の編集後記 例文集(短文・中文・フルバージョン)
この章では、すぐに使える短文や中文、そしてそのまま使えるフルバージョンの例文を、用途別にご紹介します。
ビジネス向けからカジュアルまで、編集後記の用途ごとに豊富に揃えているので、そのままコピーして少し手を加えるだけで完成できます。
企業広報誌・ビジネス向け
<短文例(3例)>
・紅葉の候、皆さまに深まる秋の彩りをお届けできれば幸いです。
・秋冷の候、日ごとに気配が深まるなか、引き続きご注目いただけますようお願い申し上げます。
・錦秋の候、皆さまにとって充実した季節でありますように。
<中文例(2例)>
・秋晴れの空が冴え渡るこのごろ、読者の皆さまには新たな季節の風を感じていただけるとうれしく思います。
・深まる秋の趣をお届けする今号が、皆さまの心にそっと寄り添う存在になれれば幸いです。
<フルバージョン例文(500字前後)>
晩秋の候、木々の錦色が街を覆い、日々が深まりを増しています。今号では働き方の変化と、それに伴う働く人々の想いに焦点をあててお届けしました。私自身も、同じ記事を紡ぐ一員として、働き方を改めて見つめ直す機会をいただいたように感じています。秋の気配がますます強くなるなか、読者の皆さまにも新しい発見や小さな感動が訪れますようお祈り申し上げます。
社内報・学校・地域向け
<短文例(3例)>
・初秋の候、校庭の木々も少しずつ色づき、季節の移ろいを感じるころとなりました。
・爽秋の候、地域の文化祭が近づき、子どもたちの声に心が暖まります。
・秋晴れの候、秋の日差しの中で皆さんの笑顔が浮かぶようです。
<中文例(2例)>
・秋風に揺れる落ち葉を眺めながら、児童たちの元気な笑顔を思い浮かべています。
・豊かな実りの季節を迎え、地域の皆さまの支えがあって今号が完成しました。
<フルバージョン例文(500字前後)>
爽秋の候、校庭の木々が赤や黄で彩られ、息をのむような景色に包まれています。今号では文化祭と学びの語りを中心にまとめましたが、準備に励む児童たちの姿や、教職員の皆さんのチームワークにも心温まる瞬間がたくさんありました。こうした秋の彩りと一緒に、この編集後記が皆さまの心にそっと寄り添うことができればうれしく思います。
カジュアル向け
<短文例(3例)>
・秋涼の候、秋の虫たちの声に耳を傾ける季節ですね。
・錦秋の候、そろそろ温かい飲み物が恋しくなるころです。
・秋晴れの候、気持ちのいい風が心地よく感じられます。
<フルバージョン例文(500字前後)>
秋晴れの候、澄んだ青空と穏やかな風に、一息つける時間が増えてきました。最近は、近所の並木道を歩きながら、足元の落ち葉を踏みしめるひそかな楽しみに心が和んでいます。この編集後記を通して、皆さまとそんな“ほっとする秋のひととき”を共有できれば幸いです。どうぞこれからも、秋の空気を感じながら心地よい時間をお過ごしください。
| 用途 | 短文 | 中文 | フル例文 |
|---|---|---|---|
| 企業向け | 3例 | 2例 | 1例 |
| 社内報・学校・地域向け | 3例 | 2例 | 1例 |
| カジュアル向け | 3例 | ― | 1例 |
これだけの例文があれば、目的別に選んですぐ使えるので、編集後記作成がぐっとスムーズになります。
秋に使える便利フレーズ・ネタ集
「季節感を入れたいけど、毎回違う言い回しを考えるのが大変…」という方におすすめなのが、使い回せる便利なフレーズ集です。
編集後記にさりげなく使うことで、秋らしさがぐっと引き立ちます。
ここでは、自然や風物詩・食べ物・行事など、テーマ別に活用しやすい表現をご紹介します。
自然・風物詩に関するフレーズ
秋の自然や風景は、視覚的にも感情的にも読者の共感を呼びやすい素材です。
文章の中にさりげなく盛り込むだけで「秋らしさ」が伝わります。
| 使えるフレーズ | 使い方のヒント |
|---|---|
| 木々の彩りが美しい季節となりました。 | 紅葉に関する挨拶や締めに最適 |
| 空が高く澄み渡る秋晴れの日が続いています。 | 自然な導入の一文として |
| 虫の音が心地よく響く夜が増えてきました。 | 秋の夜長を表現する際に |
| 街を歩くと、コスモスやすすきが風に揺れています。 | 視覚的な情景描写に |
| 朝夕の風に、秋の深まりを感じるようになりました。 | 時候の挨拶の後に添えると自然 |
秋の食べ物・文化行事に関するフレーズ
「食欲の秋」「芸術の秋」「読書の秋」など、秋は話題の宝庫。
読者の五感に訴える言葉を入れると、共感や想像が膨らみます。
| 使えるフレーズ | 使い方のヒント |
|---|---|
| 焼き芋の香りが漂い、秋の訪れを実感しています。 | 秋のグルメシーンの描写に |
| 栗や柿、さつまいもなど、旬の味覚が店頭を賑わせています。 | 季節の話題のきっかけに |
| 読書の秋にちなんで、最近は寝る前に本を読むのが習慣です。 | パーソナルな導入に |
| ハロウィンの装飾が街に広がり、秋の楽しさを感じます。 | 10月下旬の話題として◎ |
| 文化祭や運動会など、秋ならではのイベントも目白押しですね。 | 地域・学校系の話題で |
これらのフレーズをストックしておくと、「書き出しに困る…」というときにとても便利です。
編集後記ごとに違った季節感を演出でき、読む人にも「丁寧に書かれているな」と感じてもらえるはずです。
秋の編集後記を書くときの注意点
秋の編集後記は季節感が出しやすい分、つい似たような表現や構成になってしまうことも。
この章では、毎回「読まれる」編集後記にするために意識したいポイントや、避けたほうが良い表現についてまとめます。
読みやすい長さとバランスの取り方
編集後記の長さは300〜500字前後が目安です。
短すぎると味気なく、長すぎると最後まで読まれない可能性があります。
文章構成としては、以下のような流れを意識するとスムーズです。
| パート | 内容 | 目安の文字数 |
|---|---|---|
| 冒頭 | 時候の挨拶・季節感の提示 | 〜100字 |
| 中盤 | 体験談や話題・読者への語りかけ | 200〜300字 |
| 結び | 気遣いや前向きな締め言葉 | 〜100字 |
硬すぎず柔らかすぎない表現
ビジネス向けでもカジュアルでも、文体は「丁寧さ」と「親しみやすさ」のバランスが大切です。
たとえば「〜でございます」のような硬い敬語を多用すると、よそよそしく感じられることもあります。
一方、くだけすぎた口語表現(「〜だよね」「うれしいよね」など)は、文脈によっては軽すぎる印象を与えかねません。
です・ます調を基本に、読みやすく自然な語り口を目指しましょう。
同じ季語や表現を繰り返さない工夫
秋の編集後記は毎年何度も書くことになるため、どうしても表現がマンネリ化しがちです。
「秋晴れ」「紅葉」「読書の秋」などは便利な言葉ですが、使いすぎると印象が薄くなります。
その場合は、類語や言い換え、あるいは「個人的な視点」で描写するのがおすすめです。
| ありがちな表現 | 言い換え・工夫例 |
|---|---|
| 秋晴れが気持ち良い | 「雲ひとつない空に金木犀の香りが漂い」など五感に訴える表現 |
| 紅葉がきれい | 「足元に落ちた赤や黄の葉がカーペットのようでした」など視覚的描写 |
| 読書の秋 | 「最近は湯たんぽ片手に、夜長の読書を楽しんでいます」など具体的シーン |
ありきたりを避けるには、「自分らしい視点」と「五感の描写」が強い武器になります。
まとめ:豊富な例文を活用して秋の編集後記を完成させる
秋は、自然の変化や行事が多く、季節感を表現しやすい時期です。
そんな秋にふさわしい編集後記は、読者との距離を縮め、情報に温かみを添える大切な要素となります。
本記事では、秋の編集後記を書くための基本ルールから、9月〜11月に使える時候の挨拶、そして実際に使える例文を多数ご紹介しました。
短文・中文・フルバージョンの例文を揃えることで、どんな媒体やシーンでも対応できるようになっています。
特に意識したいのは、次の3つのポイントです。
| ポイント | 具体的な意識づけ |
|---|---|
| 季節感をしっかり入れる | 時候の挨拶+自然や風物詩の話題を盛り込む |
| パーソナルな語り口 | 自分の体験やちょっとした日常を入れて「人の声」を出す |
| 丁寧で自然な締めくくり | 読者を気遣い、前向きな一文で締める |
例文はそのまま使ってもよし、自分の言葉に少しだけ置き換えてもよし。
大切なのは、「その時その場の空気感を伝える気持ち」です。
今回の記事を参考に、ぜひ“あなたらしい秋の編集後記”を楽しんで書いてみてください。
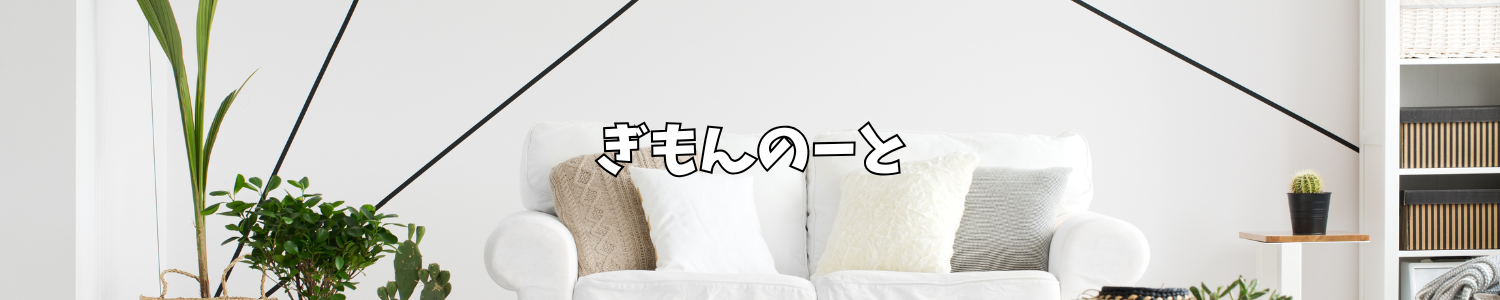
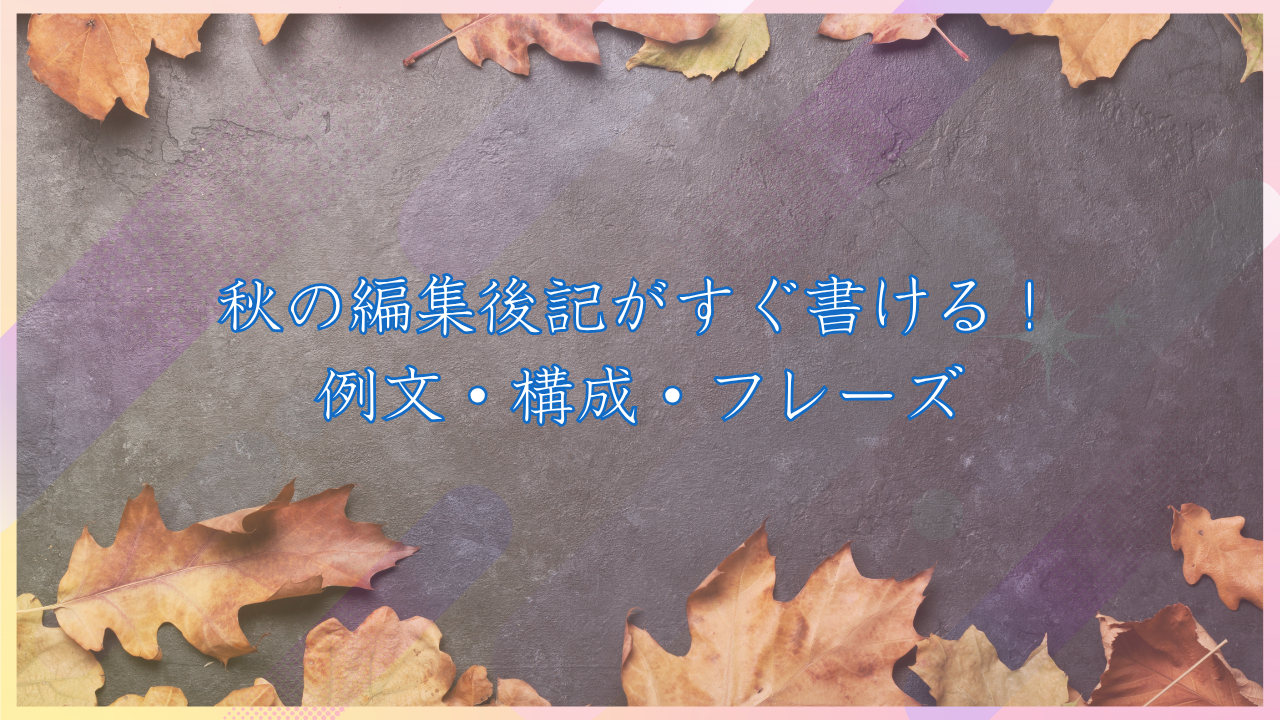
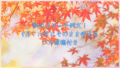
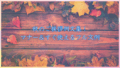
コメント