七五三は、お子さまの健やかな成長を祝う日本の伝統行事です。
その際に欠かせないのが「初穂料」ですが、いざ準備をしようとすると「いくら包めばいいの?」「のし袋にはどう書くの?」「住所は必要?」と迷う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、七五三の初穂料について金額の相場、のし袋の選び方、表書きや住所の正しい書き方をわかりやすくまとめました。
さらに、お金の入れ方や渡すタイミング、ふくさの使い方など、当日慌てないためのマナーも詳しくご紹介します。
初めての七五三でも安心して準備できるよう、ポイントを一つひとつ丁寧に解説していますので、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
七五三で必要な『初穂料』とは?
七五三のお参りをする際に欠かせないのが「初穂料」です。
ここでは、初穂料の意味や歴史的な背景、また似ている「玉串料」との違いをわかりやすく解説します。
七五三で必要な「初穂料」とは?
初穂料の意味と由来
「初穂料(はつほりょう)」とは、ご祈祷をお願いするときに神社へ納める謝礼のことです。
昔はその年に初めて収穫した稲穂を神様へ捧げていたことから「初穂」と呼ばれるようになりました。
時代とともにお米や作物ではなくお金で感謝を表す習慣に変化し、現在では祈祷料として現金を納めるのが一般的です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 読み方 | はつほりょう |
| 意味 | 神社での祈祷や祭事に納める謝礼 |
| 由来 | その年の初めての収穫物を神様に捧げた風習 |
玉串料との違い
「玉串料(たまぐしりょう)」も神社に納める謝礼として使われる言葉ですが、用途に違いがあります。
玉串とは榊の枝に紙垂(しで)をつけた神前のお供えで、本来はそれを捧げる儀式があります。
現代ではお供えの代わりに現金を納める場合に「玉串料」と表現されます。
ただし、七五三などのお祝い事では「初穂料」と書くのが正しいマナーです。
| 項目 | 初穂料 | 玉串料 |
|---|---|---|
| 使用シーン | 七五三・お宮参りなど慶事 | 慶事・葬儀など幅広い神道行事 |
| 意味 | 収穫物の代わりに納める謝礼 | 玉串の代わりに納める謝礼 |
| 表書き | 「初穂料」「御初穂料」 | 「玉串料」「御玉串料」 |
七五三の準備をする際には、必ず「初穂料」と表記しましょう。
七五三の初穂料の金額相場
初穂料はいくら納めればよいのか迷う方も多いですよね。
ここでは、七五三の一般的な金額相場、兄弟姉妹で参拝する場合の考え方、有名神社の具体的な金額例をまとめてご紹介します。
七五三の初穂料の金額相場
一般的な相場(5,000〜10,000円)
七五三の初穂料は、全国的に5,000円〜10,000円が目安です。
多くの神社では金額が決まっているわけではなく、祈祷の内容や授与品(お札やお守り)の有無によって変わります。
「5,000円〜10,000円なら失礼にならない」と覚えておくと安心です。
| 金額 | 特徴 |
|---|---|
| 5,000円 | 基本的なご祈祷、授与品はお札やお守り程度 |
| 10,000円 | より丁寧な祈祷、記念品付きや家族同席可などの場合あり |
兄弟姉妹で参拝する場合の考え方
兄弟姉妹で一緒に祈祷を受けるときは人数分を用意するのが基本です。
例えば、1人5,000円の場合、兄弟2人なら合計10,000円を納めます。
ただし神社によっては二人目から割引があるケースもあるので、事前に確認すると良いでしょう。
| ケース | 初穂料 |
|---|---|
| 子ども1人 | 5,000〜10,000円 |
| 子ども2人 | 10,000〜20,000円(神社によっては割引あり) |
| 子ども3人 | 15,000〜30,000円(同上) |
有名神社の具体的な金額例
全国の有名神社では初穂料の設定が明確に決まっていることも多いです。
以下は代表的な神社の一例です。
| 都道府県 | 神社名 | 初穂料 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道神宮 | 5,000円〜 |
| 東京 | 明治神宮 | 5,000円・10,000円・30,000円 |
| 大阪 | 枚岡神社 | 6,000円〜(兄弟割引あり) |
| 福岡 | 太宰府天満宮 | 5,000円 |
参拝予定の神社の公式サイトや電話で確認しておけば、当日に迷うことがありません。
不安な場合は事前に問い合わせをしておくのがベストです。
初穂料ののし袋と封筒の選び方
初穂料を用意するときに迷いやすいのが「どんなのし袋を使うべきか」という点です。
ここでは、七五三にふさわしいのし袋の種類と、のし袋がない場合の代替方法について解説します。
初穂料ののし袋と封筒の選び方
紅白蝶結びが基本
七五三で使うのし袋は、紅白の蝶結びが定番です。
蝶結びは「何度あっても良いお祝い」に使う結び方で、子どもの成長を願う七五三に最適です。
文房具店や百円ショップでも手軽に購入できるので、事前に準備しておきましょう。
| 水引の種類 | 意味 | 用途 |
|---|---|---|
| 蝶結び | ほどいて何度でも結べる | 七五三、出産祝い、入学祝いなど |
| 結び切り | 一度結ぶとほどけない | 結婚祝い、快気祝い |
| あわじ結び | 末永い縁を願う | 謝礼や弔事 |
のし袋がない場合は白封筒でもOK
万一のし袋が用意できない場合でも、無地の白封筒で代用できます。
ただし、その際も必ず表面に「初穂料」と記入し、裏面には金額と住所を書くのがマナーです。
最近は、紅白の水引が印刷されたタイプの封筒も販売されているため、急ぎのときはそれを活用しても問題ありません。
| 封筒の種類 | 使用可否 |
|---|---|
| 紅白蝶結びののし袋 | ◎(最も一般的) |
| 紅白印刷の封筒 | ○(代替可) |
| 無地の白封筒 | △(最終手段として可) |
大切なのは「丁寧に気持ちを込めて準備すること」です。
のし袋の形式よりも、誠意を持って準備する姿勢が何よりも大切と覚えておきましょう。
七五三の初穂料の書き方(表書き編)
のし袋を用意したら、次に大切なのが表書きの記入方法です。
この章では、表書きに書く文字の内容や位置、子どもの名前の書き方、さらにお寺で七五三を行う場合の注意点について解説します。
七五三の初穂料の書き方(表書き編)
「初穂料」と書く位置と注意点
のし袋の表面、水引の上段中央に「初穂料」と記入します。
「御初穂料」としても問題ありませんが、一般的には「初穂料」で十分です。
道具は毛筆や筆ペンを使用し、ボールペンは避けるのがマナーです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 記入文字 | 初穂料 または 御初穂料 |
| 位置 | 水引の上段中央 |
| 道具 | 毛筆・筆ペン(ボールペン不可) |
子どもの名前の書き方(連名のルール)
水引の下段中央には、祈祷を受ける子どものフルネームを書きます。
兄弟姉妹で一緒に祈祷を受ける場合は、年齢の高い子から順に右から左へ連名で書きましょう。
3人の場合は真ん中に一番年下の名前を入れるなど、バランスを考えると見やすくなります。
| ケース | 書き方の例 |
|---|---|
| 子ども1人 | 山田 太郎 |
| 子ども2人 | 右から「山田 太郎」「山田 花子」 |
| 子ども3人 | 右から「山田 太郎」「山田 次郎」「山田 花子」 |
お寺で七五三を行う場合の表書き
七五三は神社だけでなく、お寺で行うケースもあります。
その場合は表書きを「御布施」と書くのが一般的です。
同じ七五三でも、神社では「初穂料」、お寺では「御布施」と書き分ける点に注意しましょう。
| 場所 | 表書きの文字 |
|---|---|
| 神社 | 初穂料・御初穂料 |
| お寺 | 御布施 |
表書きは、神職や僧侶が一目で分かるよう丁寧に書くことが大切です。
七五三の初穂料の書き方(中袋・住所編)
のし袋の表書きができたら、次は中袋や住所の記入です。
中袋がある場合とない場合で書き方が異なるので、それぞれのパターンを整理してご紹介します。
七五三の初穂料の書き方(中袋・住所編)
金額の正しい書き方(大字の使い方)
中袋の表面中央には金額を縦書きで記入します。
「5,000円」なら「金伍仟円」、「10,000円」なら「金壱萬円」といったように、改ざん防止のために大字(漢数字)を用います。
| 通常の漢数字 | 大字 |
|---|---|
| 一 | 壱 |
| 二 | 弐 |
| 三 | 参 |
| 五 | 伍 |
| 千 | 仟 |
| 万 | 萬 |
例:「金伍仟円」「金壱萬円」
住所を書く理由と正しい書き方
中袋の裏面左下には、住所と子どもの名前を縦書きで記入します。
住所を書くのは、神職が誰からの初穂料かを明確に把握するためです。
省略せず都道府県から番地・マンション名までしっかり書きましょう。
| 書き方 | 例 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1丁目1-1 ○○マンション101 |
| 氏名 | 山田 太郎 |
兄弟姉妹の場合は、同じ住所の下に連名で書くと良いです。
中袋がない場合の裏面の書き方
中袋が付いていないのし袋や、白封筒を使う場合はのし袋の裏面左下に直接記入します。
金額と住所・子どもの名前を縦書きにすれば問題ありません。
| 場所 | 書く内容 |
|---|---|
| 裏面左下 | 金額・住所・子どもの氏名 |
記入は必ず毛筆や筆ペンを使い、ボールペンは避けましょう。
「お金の入れ方とマナー
のし袋と中袋の記入が終わったら、最後に大切なのがお金の入れ方とマナーです。
ここでは、新札を準備するべきかどうか、お札の正しい入れ方、さらに「ふくさ」の使い方について解説します。
お金の入れ方とマナー
新札は必要?お札の向きと注意点
七五三の初穂料に使うお札はなるべく新しいものを準備しましょう。
銀行で両替すればピン札を用意できますが、どうしても難しい場合は折れや汚れのないきれいなお札を選べば問題ありません。
入れ方の基本はお札の肖像が表・上に来るように入れることです。
| 入れ方のポイント | 解説 |
|---|---|
| お札の向き | 肖像が表・上に来るように入れる |
| 折り目 | 折り目のないきれいなお札を使用 |
| お札の枚数 | 複数枚の場合は揃えて入れる |
ふくさに包む意味と使い方
初穂料を包んだのし袋は、さらにふくさ(袱紗)に包んで持参すると丁寧です。
ふくさは大切なものを保護し、相手への敬意を示す道具とされています。
七五三は慶事なので、赤やオレンジなどの明るい色のふくさを選びましょう。
| ふくさの色 | 用途 |
|---|---|
| 赤・橙・桃色系 | 慶事(七五三・結婚式など) |
| 紫 | 慶事・弔事どちらでも使用可 |
| 紺・緑・灰色系 | 弔事(葬儀など) |
のし袋を直接バッグに入れると折れたり汚れたりすることがあります。
そのため、必ずふくさに包んで持参するのがおすすめです。
初穂料を渡すタイミングとマナー
準備が整ったら、最後に気になるのが初穂料を渡すタイミングやマナーです。
ここでは、神社での渡し方、受付での流れ、そして渡すときの言葉について解説します。
初穂料を渡すタイミングとマナー
渡す場所と受付での流れ
初穂料は祈祷の申し込みをするタイミングで神社に納めます。
多くの神社では、社務所や受付に祈祷申込書が用意されており、必要事項を記入したうえで初穂料を渡す流れです。
神社によっては「祈祷前」に納める場合と「祈祷後」に納める場合があるので、受付で確認すると安心です。
| 渡すタイミング | 特徴 |
|---|---|
| 祈祷前 | 申込書提出と同時に納める(一般的) |
| 祈祷後 | 祈祷終了後に渡す(神社によって異なる) |
渡すときの言葉の選び方
渡す際に特別な決まり文句はありません。
ただし、神前にお供えするお金であるため、受付では「よろしくお願いします」や「お納めください」といった丁寧な言葉を添えるのが好ましいです。
堅苦しい言葉を考える必要はなく、気持ちを込めて伝えることが大切です。
| 場面 | 言葉の例 |
|---|---|
| 受付で渡すとき | 「よろしくお願いします」 |
| 神職に渡すとき | 「お納めください」「お捧げいたします」 |
初穂料は形式だけでなく、感謝の気持ちを込めて渡すことが一番大切です。
七五三で初穂料以外にかかる費用
七五三では初穂料の準備が中心ですが、それ以外にもさまざまな費用がかかります。
ここでは、代表的な「着物代」「記念撮影」「食事会」の3つについて解説します。
七五三で初穂料以外にかかる費用
着物代(購入・レンタル)
七五三といえば着物が欠かせません。
購入する場合は1万円〜10万円台が相場で、高級品では30万円以上するものもあります。
一方、レンタルなら6千円〜2万円台で用意でき、サイズアウトの心配がないため人気です。
| 方法 | 相場 | 特徴 |
|---|---|---|
| 購入 | 1〜10万円以上 | 選択肢が豊富・記念として残せる |
| レンタル | 6千〜2万円台 | 費用を抑えられる・成長に合わせやすい |
記念撮影の費用相場
写真撮影はスタジオ撮影と出張撮影に分かれます。
スタジオ撮影は3万〜12万円程度で、衣装・ヘアメイク込みが一般的です。
出張撮影は1万〜5万円程度で、参拝と同時に撮影できるメリットがあります。
| 撮影方法 | 相場 | 特徴 |
|---|---|---|
| スタジオ撮影 | 3万〜12万円 | 衣装・アルバム付きが多い |
| 出張撮影 | 1万〜5万円 | 参拝と同時に撮影できる |
食事会にかかる費用
七五三の後に親族で食事会を開くご家庭も多いです。
外食の場合は1人3千〜1万円程度、自宅で仕出しやケータリングを利用すれば1人2千〜4千円程度が相場です。
無理に行う必要はありませんが、子どもの成長を祝う良い機会となります。
| 場所 | 相場 | 特徴 |
|---|---|---|
| 外食(ランチ) | 1人3千〜5千円 | 準備や片付け不要 |
| 外食(ディナー) | 1人1万円前後 | 格式のある雰囲気で祝いができる |
| 自宅(仕出し・ケータリング) | 1人2千〜4千円 | 費用を抑えられる・リラックスできる |
初穂料以外にも費用がかかるため、全体の予算を事前に組んでおくと安心です。
まとめ|七五三の初穂料の正しい書き方と住所記入のポイント
ここまで、七五三で必要な初穂料について、金額の相場やのし袋の選び方、表書き・中袋の書き方、住所の記入方法、渡し方やマナーなどを解説してきました。
最後に、重要なポイントを整理しておきましょう。
まとめ|七五三の初穂料の正しい書き方と住所記入のポイント
- 初穂料とは:神様に感謝を込めて納める祈祷料のこと。七五三などの慶事では「初穂料」と書くのが基本。
- 金額の目安:一般的には5,000〜10,000円。兄弟姉妹は人数分を準備する。
- のし袋の選び方:紅白蝶結びが基本。用意できない場合は白封筒でも可。
- 表書き:上段に「初穂料」、下段に子どものフルネーム(兄弟は右から年長順に)。
- 中袋・住所の書き方:表に大字で金額、裏に住所と名前。中袋がない場合はのし袋裏面に記入。
- お札の入れ方:肖像が表・上に来るように。なるべく新札を使う。
- 渡すタイミング:祈祷の申し込み時に受付へ。言葉は「よろしくお願いします」で十分。
- その他の費用:着物代、記念撮影、食事会なども考慮して予算を立てる。
七五三はお子さまの健やかな成長を願う大切な節目の行事です。
正しいマナーを押さえておけば、不安なく当日を迎えられます。
準備に迷ったら、参拝予定の神社へ事前に確認するのも安心につながります。
ぜひこの記事を参考に、心を込めて七五三をお祝いしてください。
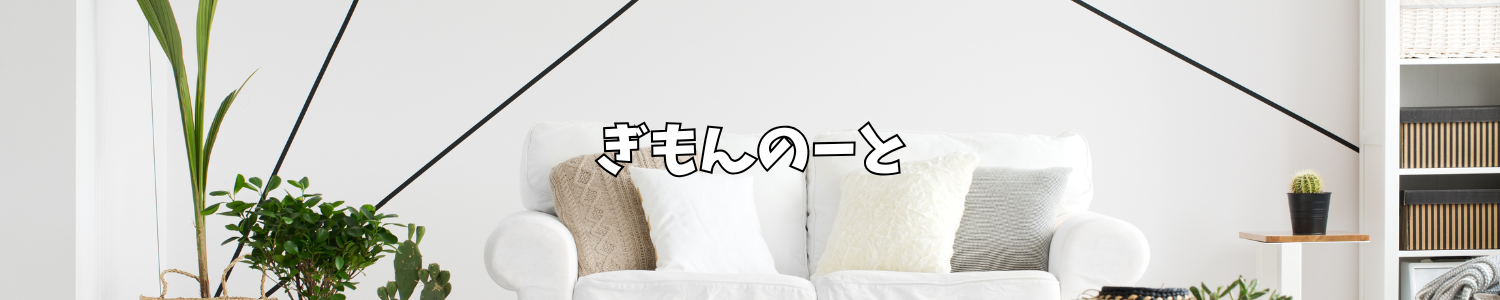
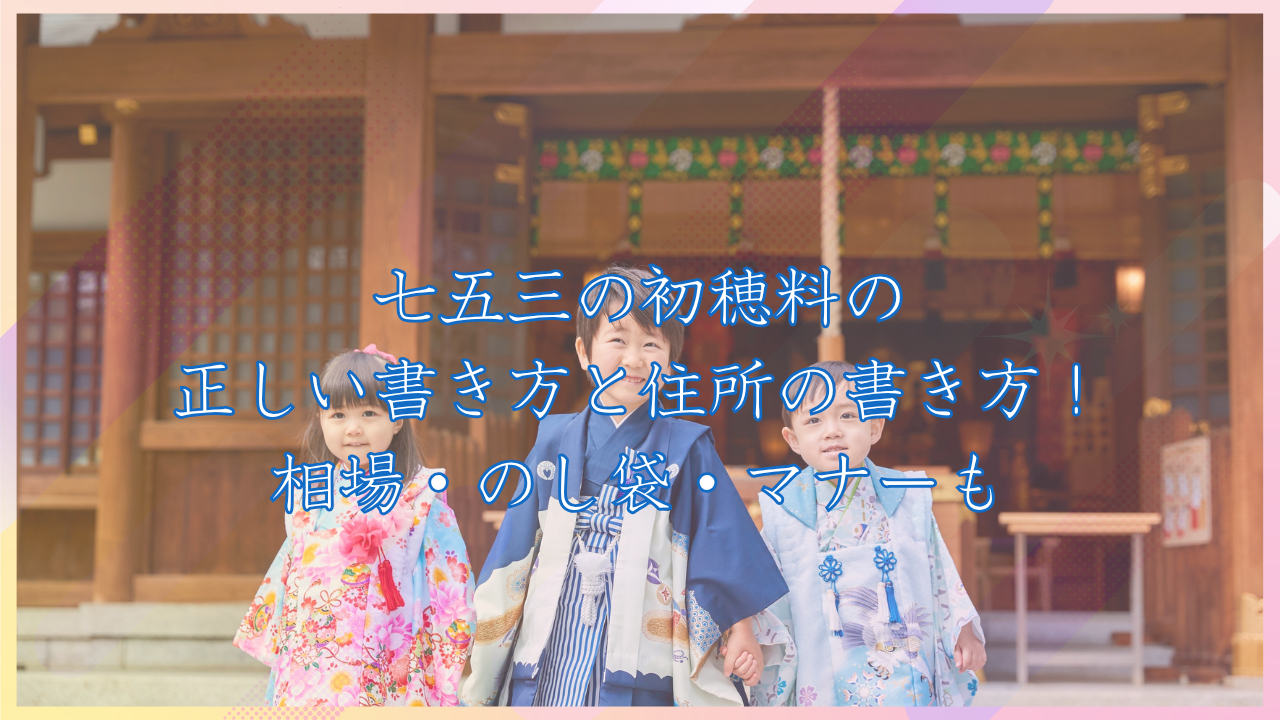

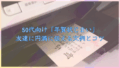
コメント